はじめに
※この記事はシリーズの第4回です。過去の記事はこちらからご覧いただけます:
なお、今回ご紹介する生活習慣の工夫は、前回お伝えした“セロトニンを増やす栄養”の土台があってこそ、より効果を発揮します。
食事でセロトニンの材料がきちんと届いているからこそ、日々の光やリズムがその力を引き出してくれるのです。
- セロトニンを整える暮らし①:セロトニンって何? ― 繊細さと脳の関係
- セロトニンを整える暮らし②:無理にがんばらず、戻る力を育てる“静かな習慣”
- セロトニンを整える暮らし③:セロトニンを増やすには?朝・昼・夜にできるやさしい食習慣のヒント
「セロトニンを増やすにはどうすればいいのか」
きっと、これを検索してたどり着いた方も多いのではないでしょうか。
ですが、いざ“増やす方法”を探し始めると、
運動、日光浴、朝活、ヨガ、食事管理…と、やることがどんどん増えていって、
気づけば、
「心を整えるはずが、がんばり疲れてしまう」
ということも。
HSP気質のある方ならなおさら、
情報の多さに気持ちが追いつかなくなることもあるかもしれません。
でも、本当に必要なのは、
「がんばらずに整っていく」やさしい仕掛け
なのだと、私は思うのです。
少しの光。
少しのリズム。
そして、自分に気づいてあげる一瞬。
それだけでも、体の中では確かに変化が起きている――
そう実感できるようになった、私自身の体験をお伝えさせてください。
朝の太陽が、体と心のスイッチを入れる
セロトニンが活性化する一番のタイミングは、朝の光を浴びたときです。
実は、朝の太陽の光は、
その日の活動のスイッチを入れるだけでなく、次の夜の“眠りの準備”にも影響します。
これは、脳幹にあるセロトニン神経が、目から入る光の刺激で活性化するしくみによるもの。
つまり、「朝に光を浴びる」ことは、セロトニンのスイッチを入れてくれる自然な合図なんですね。
私の家は東向きのマンションで、寝室には朝日がしっかり差し込んできます。
……でも、夜になると外廊下の照明がまぶしくて、遮光カーテンが手放せない。
結果として、朝の光に気づけないまま起きる日々が続いていました。
そんなときに見つけたのが、自動でカーテンを開けてくれる装置でした。
「朝が苦手で、カーテンを開けるのもつらい」
そんな方には、ぜひ知ってほしいアイテムです。
自分の代わりに光を届けてくれるその仕組みが、我が家では心地よい変化をくれました。
リズム運動は、体を動かすことだけじゃない
セロトニンは、一定のリズムで繰り返す動きによって活性化されます。
この「リズム運動」は、何も激しい運動に限りません。
たとえば、歩く・揺れる・呼吸する・噛む。
こうした日常のなかにあるリズムこそが、脳にとっての心地よい刺激になります。
ラジオ体操 ― 音楽と体のリズムをつなげて
私が取り入れているのは、3分間のラジオ体操です。
音楽が流れると自然に体が動く――これは義務教育のすごさかもしれません(笑)
私はアレクサに「ラジオ体操かけて」とお願いして、気が向いたときに体を動かしています。
無理して毎日じゃなくても、「体にリズムを感じさせる」だけでも意味がある
子どもも大人も「揺れて整う」トランポリンのすすめ
もうひとつ、リズムを感じる習慣として私が取り入れているのが、トランポリンです。
トランポリンは、子どもにとっては遊び、大人にとってはセロトニン活性に役立つ道具。
上下に揺れるリズムが、脳幹をやさしく刺激してくれると言われています。
うちの子もトランポリンが大好きでした。
でも、以前しまってあった大型のものを取り出そうとしたとき、
バネが開いて顔を強打してしまったことがあり、それ以来しまいっぱなしに……。
そんな私が最近出会ったのが、インテリアにもなじむ安全設計のトランポリンでした。
跳ねるというより、“そっと揺れる”だけでも十分。
ソファーとして使えるものもあり、スペースを取らずにリビングに置ける。
「子どものため」だけでなく、「自分の整え時間」として使えるのが気に入っています。
噛むことも、大切なリズム運動
意外に見落とされがちですが、「噛む」ことも立派なリズム運動です。
特に、ガムを一定のリズムで噛むと、セロトニン神経が刺激され、気分の安定につながるという研究もあります。
実際、リズムよく噛むことで脳幹が刺激され、セロトニンの活性につながることがわかっています
ただし、顎関節症などがある方や、HSPの方で「無意識の食いしばり」を抱えている場合は、無理のない範囲で。
小さなリズムを、自分の心地よい形で取り入れる
それがいちばんのコツかもしれません。
呼吸が速いと、疲れは抜けにくい
施術中にお客様の様子を見ていると、眠っているのに呼吸がとても速い方が多いのです。
これは、交感神経が過剰に働いた状態で、深い休息には入りにくい傾向。
呼吸回数が多いこと自体に気づかない方も多いため、Apple Watchなどで可視化することは、自覚と改善の第一歩になると感じています。
でも、「呼吸を整えよう」と意識するほど、呼吸は不自然になりがち。
だから私は、まずこう伝えるようにしています:
「呼吸を整えるのではなく、呼吸が整いやすい状態に体をゆるめることから始めましょう」
たとえば、
- 肩をすくめてからストンと落とす
- 背中を丸めてゆっくり息を吐く
- 息を吐きながら手のひらをゆっくり開く
こんな動作だけでも、副交感神経の働きが優位になっていきます。
リズムとは、安心をくれる「波」
ここまでお伝えしてきたように、セロトニンはリズムによって育ちます。
リズムとは、決まった動きを、無理なく、繰り返すこと。
- 歩く
- 噛む
- 揺れる
- 呼吸する
- 音楽に合わせて動く
このどれもが、体と心に波を起こし、その波がやがて落ち着きをくれる。
「がんばって何かをする」より、「そっと寄り添ってくれるものに自分をゆだねる」
そのほうがずっと整いやすい――HSPの方には、そんな方法がぴったりかもしれません。
終わりに
セロトニンを育てることは、特別なことではありません。
ほんの少し、「いつもと違うこと」をしてみるだけで、体はちゃんと気づいてくれます。
朝の光。
3分のラジオ体操。
呼吸に気づく。
どれも、大きな変化ではないけれど、
**「あ、気持ちいいかも」**という感覚が、そのまま整う方向へのスイッチになります。
今日も、あなたの中のセロトニンが、そっと育ちますように。
この記事を書いた人
いっしたまえ|心と体を整えるアドバイザー
敏感アンテナさんたちに寄り添いながら、
自律神経と眠りを整えるヒントをお届けしています。
元看護師・セロトニン活性アドバイザーとして、
「眠れる体と疲れない心に整える」サロン Calm time を運営。
自身と家族の体験を通して、心と体を支える知恵を発信しています。
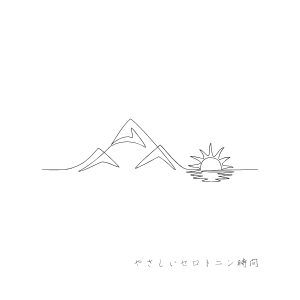
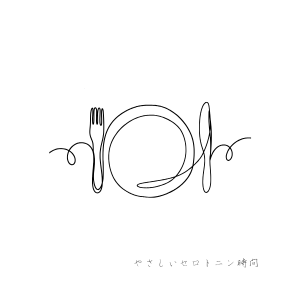
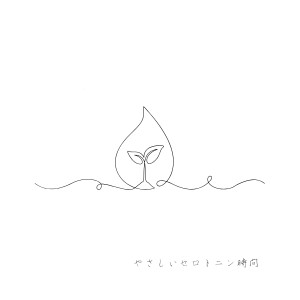
コメント