特に**HSP(繊細な感受性を持つ人)**と言われるような方にとって、
日常の刺激やストレスは、想像以上に大きな負担になっていることがあります。
- 音や光、人の気配
- ちょっとした言葉や空気の変化
そうした“外からの刺激”を強く受けやすいからこそ、
日々の中で感じる疲れやすさ、不安定さには、ちゃんと理由があるのかもしれません。
そんな私たちにとって、**「セロトニン」**という存在を知っておくことは、
自分をいたわりながら暮らしていくための“ひとつの支え”になるはずです。
この記事の内容
- セロトニンとは何か?どうして大切なのか
- 現代の暮らしがセロトニンに与える影響
- セロトニンが不足するとどうなるのか
- 繊細な人(HSP)にとっての重要性
- セロトニンを整えるための4つの基本習慣
セロトニンって何?昔の人は知らなかったのに
「セロトニン」。
この言葉を初めて聞く方も多いかもしれません。
そして、こんなふうに思うかもしれません。
「そんなもの知らなくても、みんな普通に生きてきたじゃない」
たしかにそうです。
飢きんがあっても、戦争があっても、
私たちの祖先は、セロトニンの存在なんて知らずに乗り越えてきました。
それでも生きられたのは、
**“セロトニンが自然と育まれる暮らし”**がそこにあったから。
- 朝になれば目覚める
- 歩いて働く
- よく噛んで食べる
- 誰かと語り合い、寄り添い、感謝を伝えながら眠る
そんな“人間らしい時間”の中で、
セロトニンは自然に分泌され、私たちを守ってくれていたのです。
でも今、社会は大きく変わりました。
- 朝日を浴びずに暮らせる家
- 噛まなくても飲める食事
- 孤独でもつながった気になれるSNS
私たちのDNAは何万年もかけてできたのに、たった数十年で生活が激変してしまった。
だからこそ、今あらためて――
**「セロトニンを意識して整える」**という選択が、必要になってきているのです。
私に起きていたこと──セロトニン不足に気づいたとき
私自身、以前はセロトニンのことなんて意識せずに、ごく普通の生活を送っていました。
でも今振り返ってみると、あの頃の私は、セロトニンが足りていなかった状態だったのかもしれません。
- 眠っても疲れが取れない
- 感情の波が激しい
- 集中力が続かない
それらのひとつひとつは、後になって「セロトニンが関係していた」と気づいたことでした。
がんばることが当たり前だった毎日。
ちょっとしたことで涙が出たり、イライラしてしまう自分に嫌気がさしたり、
まるで感情のコントロール装置が壊れたような感覚。
その空気はきっと、家族にも伝わっていたと思います。
それでも、「私さえ我慢すれば」と、ひたすら無理を続けていました。
心療内科で「セロトニンの話」を聞いたときも、
当時の私はそれを“自分ごと”として受け取る余裕すらなかったのです。
少しだけ立ち止まれるようになって、ようやく見えてきたものがありました。
疲れというより“消耗”。
気力ではなく、“感情を支える力”が静かに切れていたのだと気づけたとき、
はじめて「セロトニンがどうして必要だったのか」を理解できた気がしたのです。
セロトニンとは?──脳の中の“安心物質”
私たちの体の中には、思っている以上に**“無意識でがんばってくれている仕組み”**があります。
そのひとつが「セロトニン」という神経伝達物質。
特別な人だけのものではなく、誰の脳の中にも存在していて、
生きていくうえで自然に働いている**“生理的なしくみ”**のひとつです。
セロトニンとは、心と体のバランスを整える**“脳内の安心物質”**と言われています。
セロトニンは以下のような働きを支えています:
- 感情の安定
- 姿勢の維持
- 呼吸のリズム
- 自律神経のバランス
- ホルモン分泌の調整
脳の奥深くにある“セロトニン工場”(縫線核〈ほうせんかく〉)から分泌され、
私たちが**「心地よく、安心して生きる」**ための土台をつくってくれています。
特にセロトニンがよく働いているときには:
- 呼吸が自然と深くなる
- 姿勢が安定する
- 気持ちの浮き沈みがゆるやかになる
- 「どっしりと落ち着いた感覚」が生まれやすくなる
また、セロトニンは夜になると「メラトニン(睡眠ホルモン)」に変化します。
つまり、日中にセロトニンがしっかり分泌されていれば、
夜の眠りもスムーズになりやすいのです。
さらに、脳科学の研究を長年続けている有田秀穂教授は、
セロトニンが安定して働いている状態を
**「クールな覚醒状態(calm but awake)」**と呼んでいます(※1)。
それは、ただリラックスしているのではなく、
“静かに目覚めていて、行動できる準備が整っている”ような状態。
- やる気に満ちたテンションではなく、
- 「今、自分の足で立っていられる」ような穏やかな感覚
そんな心身の状態が、セロトニンの安定によって生まれてくるのです。
セロトニンが減ってしまう理由
本来、私たちの体にはセロトニンを分泌する機能が備わっていますが、
それがうまく働かなくなる原因のひとつが**「ストレス」**です。
現代のストレスは、かつてとは違う形で私たちを追い詰めます:
- 絶え間ない情報の流入
- 人とのつながりの希薄さ
- SNSによる比較や孤独感
- 自己否定感や過剰な期待
こうしたストレスの蓄積は、セロトニンの働きを妨げ、
結果として心と体のバランスを崩しやすくなります。
特にHSP気質の方は、些細な刺激にも過敏に反応しやすく、
本人も気づかないうちにセロトニンが消耗しやすい傾向があります。
セロトニンを整えるためにできること
セロトニンをうまく働かせるためには、
日々の暮らしの中でセロトニンを増やす方法を知り、実践していくことが大切です。
特に意識したい4つの要素は、以下の通りです:
- 朝の光を浴びる(体内時計とセロトニンを同時に整える)
- リズム運動を取り入れる(ウォーキングやラジオ体操など)
- 栄養バランスを意識する(たんぱく質、ビタミン、鉄など)
- **ふれあい(オキシトシン)**を大切にする(会話や触れ合い)
これらはすべて、セロトニンを活性化し、
心と体の安定に貢献してくれる“日常の中の小さな選択”です。
- 忙しい朝も、カーテンを開けて陽の光を浴びてみる
- 家事の合間に好きな音楽でリズムをとる
- 食事でたんぱく質やビタミンを少し意識してみる
- 大切な人との会話やペットとのふれあいを楽しむ
特別なことをしなくても、
自分のスタイルに合わせて取り入れることができる──
そんな身近な方法が、セロトニンを整える第一歩になるのです。
それぞれの具体的な方法については、今後のブログ記事でひとつずつ、ていねいにご紹介していきます。
※1:有田秀穂『脳からストレスを消す技術』(サンマーク出版)
🔗次回の記事では、まず「朝の光」とセロトニンの関係について詳しくお届けします。
「朝がつらい」「体がだるい」と感じる方にこそ、読んでほしい内容です。
📚シリーズ記事はこちら:
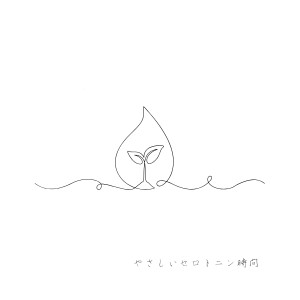
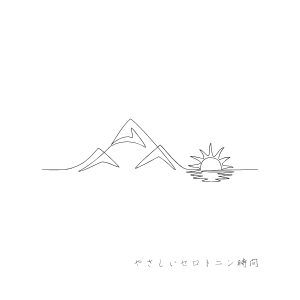

コメント