この記事は、セロトニンと心の整え方をテーマにした連載シリーズの第2回です。
今回は「セロトニンが減る理由」と「無理なく整えるための静かな習慣」について、私自身の体験をもとにお話しします。
▼ まだ読んでいない方はこちらからどうぞ
→ 第1回|気分は整えられる。幸せはつくれる
セロトニンが宿っていたのは、「本来の生活リズム」だった
私は「セロトニンを増やす方法」を調べるうちに、
それが昔の人が自然に行っていた習慣と重なることに、なんだか肩透かしをくらったような気持ちになりました。
特別な方法ではなく、昔からあるごく普通のことだったからです。
- 朝の光を浴びる
- リズムよく体を動かす
- よく噛んで食べる
- 人とふれあう
どれも、かつては当たり前にあったものばかりです。
でも現代では、それが「意識しないとできないもの」になってしまっています。
私たちの生活リズムが大きく変化したことで、セロトニンは減りやすくなったのかもしれません。
セロトニンが減ってしまうのは、生活だけのせいじゃない
確かに、夜更かし・運動不足・孤独な生活など、
セロトニンが減りやすい生活習慣はあります。
さらに、乱れた食生活や食べ方の傾向も影響します。
でもそれだけではなく、
私自身の実感としては、自分でも気づかないうちに積み重なったストレスの影響が大きかったように感じています。
敏感な人が無意識に感じているストレス
- 人の気配や存在そのものに緊張してしまう
- 表情や雰囲気を読み取りすぎて、「怒ってる?」「私のせい?」と考えてしまう
- 誰にも見られていなくても「ちゃんとしなきゃ」と思ってしまう
そして──
家族でさえも距離を置きたくなる瞬間がある。
それはわがままなんかじゃなくて、
「安心するために必要な距離」を保とうとする反応かもしれません。
こうしたストレスの蓄積は、セロトニンを消耗させてしまいます。
なぜなら、強いストレスを感じると、脳は防御反応としてノルアドレナリンやコルチゾールといったストレスホルモンを分泌します。
このとき、セロトニンの分泌や働きが抑えられてしまうと考えられているからです。
「焦り」の感覚が、整える力を奪っていた
そして私は、いつも何かに急かされているような感覚がありました。
時間に追われているわけではないのに、
“自分の中の声”が「もっと早く」とせかしていたように思います。
特に、仕事柄、食事はいつも早食い。
ゆっくり味わうことができない日々が続いていました。
焦っていると、呼吸も動きも乱れます。
リズムよく動くことができない──それも、セロトニンを整えるチャンスを逃していたのかもしれません。
今では、あたたかいものを、ゆっくり味わって食べる時間が、自分を整えてくれるひとときになっています。
この「焦りの感覚」は、HSPのように繊細な感受性を持つ人にとって、とても身近なものかもしれません。
まわりの空気を気にしたり、相手の期待に敏感に反応したり──
その繊細さが、知らず知らずのうちに「急がなきゃ」「うまくやらなきゃ」と自分を追い詰めるストレスになることもあります。
だからこそ、焦りに気づき、それをほどく時間を少しでも持つことが、セロトニンを整える第一歩になると感じています。
セロトニンが喜ぶ、生活の小さな工夫
▪ 朝の光を浴びる
起きたらカーテンを開ける。
それだけで、体内時計が整い、セロトニンが動き始める。
今では、自動で開くカーテンの存在が気になっています。
私の部屋は朝日が入る方角なのに、外廊下の照明のせいで遮光カーテンを使わざるを得ず、朝も暗いまま。
きっとこうした工夫があれば、起き方は変わるだろうと感じているところです。
▪ リズム運動を日常に取り入れる
歩く、掃除をする、料理でトントンと切る音。
どれもセロトニンを刺激する「一定のリズム」なんです。
そして──
見落とされがちだけど、重要なのが「噛むこと」。
ロッテが行った研究では、
ガムを噛むことで、脳内のセロトニンが活性化していることを示す反応が観察されたと報告されています。
私も、意識して“よく噛む食事”を心がけるようになってから、
なんとなく落ち着く感じが増えたように感じています。
▪ 腸を大切にする食事
セロトニンは脳にも腸にも関わるホルモンです。
実際には、その多くは腸に存在していますが、
感情の安定や睡眠リズムに関わるのは、脳内で働くセロトニンです。
とはいえ、腸の状態が整っていると脳にも良い影響があるとされていて、
「腸と脳はつながっている」という考え方は、最近ではよく知られるようになってきました。
私にとっては、「温かいものをゆっくり食べる」ことがいちばんの整え方でした。
人とのふれ合いが難しいときの、やさしい方法
セロトニンやオキシトシンを増やすには、
人との会話やスキンシップもひとつの方法です。
でもそれが難しい時は、自分ひとりでできる“心地よさ”を使えばいいんです。
- 肌ざわりのいい毛布にくるまる
- お気に入りのパジャマを着る
- 好きな香りのアロマを楽しむ
- 自分だけの“推し活”に没頭する
- 心地よい音楽や映像に浸る
「誰かと」ではなく、「自分がどう感じるか」。
これが、オキシトシンやセロトニンを穏やかに育ててくれる道なんだと思います。
ちょっとだけ意識的に、「セロトニンが喜ぶこと」をしてみる
セロトニンが減りやすい人はいます。
でも、それは“弱い”のではなく、“繊細さ”という強さの裏返し。
だからこそ、
がんばらずに、“別の角度”から整えていくことが大切だと思うのです。
◇ 特別なことじゃなくていい
◇ 自分のペースでできることから
◇ セロトニンを増やす行動を「自分にやさしくなる時間」として取り入れてみる
次回予告
次回は、私が実際に使ってみて「これはよかった」と感じた、
セロトニン習慣を助けてくれたアイテムたちをご紹介します。
✶ セロトニンを整える暮らしシリーズ
第1回:気分は整えられる。幸せはつくれる
第2回:今読んでる記事です
第3回:セロトニンを増やすには?朝・昼・夜にできるやさしい食習慣のヒント
この記事を書いた人
いっしたまえ|心と体を整えるアドバイザー
敏感アンテナさんたちに寄り添いながら、
自律神経と眠りを整えるヒントをお届けしています。
元看護師・セロトニン活性アドバイザーとして、
「眠れる体と疲れない心に整える」サロン Calm time を運営。
自身と家族の体験を通して、心と体を支える知恵を発信しています。

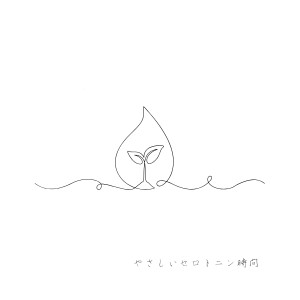
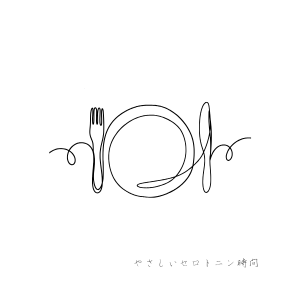
コメント