はじめに
この記事は「HSPとセロトニン」シリーズの第4回です。
繊細でがんばりすぎてしまうあなたへ。
セロトニンを整えることで「無理なく、自然に、自分らしく」戻っていける——
そんなヒントを届けたくて、体験をもとにまとめています。
今回のテーマは、“生活習慣の工夫”。
前回の「③:気づきとチェックリスト編」で、
日々の中に潜むセロトニン不足のサインに気づいた方にこそ、
ぜひ読んでいただきたい内容です。
▶ 過去の記事はこちら:
- HSPとセロトニン①:繊細なあなたに必要な“見えない土台”
https://serotonin-bliss.biz/blog/serotonin-hsp-intro/ - HSPとセロトニン②:「なぜ疲れるのか」がわかると、自分の輝き方が見えてくる
https://serotonin-bliss.biz/blog/serotonin-habit-check/ - HSPとセロトニン③:セロトニン不足チェックリストで“見えない疲れ”に気づく
https://serotonin-bliss.biz/blog/serotonin-checklist/
「セロトニンを増やすにはどうすればいいのか」
そう検索してここにたどり着いた方も、多いかもしれません。
ですが、いざ調べ始めると——
運動、日光浴、朝活、ヨガ、食事管理…と、やることがどんどん増えていって、
気づけば、
「心を整えるはずが、がんばり疲れてしまう」
ということもありますよね。
HSP気質のある方ならなおさら、
情報の多さに気持ちが追いつかなくなることもあるかもしれません。
でも、本当に必要なのは、
がんばらずに整っていく、やさしい仕掛け
少しの光。
少しのリズム。
そして、自分に気づいてあげる一瞬。
それだけでも、体の中では確かな変化が起きている。
今回は、そんな体験をもとに「セロトニンが整う毎日のつくり方」をご紹介します。
目次
- 朝の太陽が、体と心のスイッチを入れる
- リズム運動は、体を動かすことだけじゃない
- 音楽とつながるラジオ体操
- 子どもも大人も「揺れて整う」トランポリンのすすめ
- 噛むことも、大切なリズム運動
- 呼吸が速いと、疲れは抜けにくい
- リズムとは、安心をくれる「波」
- おすすめアイテムまとめ(アフィリエイト)
- おわりに
朝の太陽が、体と心のスイッチを入れる
朝の光は、私たちの体と心にとって、1日の“スタート合図”です。
セロトニンが活性化する一番のタイミングは、朝の光を浴びたとき。
目から入る光が脳幹にあるセロトニン神経を刺激して、
体を「目覚めさせるモード」に切り替えてくれます。
そのスイッチが入ることで、
- 日中は活動的になりやすい
- 夜には眠りを誘う“メラトニン”がつくられる準備が始まる
- 体温や血流が整い、頭も冴えてくる
- 自律神経が自然と日中モードへ移行していく
つまり、朝の光は1日のリズムを整える“やさしい起動スイッチ”なんですね。
特に「朝がつらい」「起きてもだるさが抜けない」と感じる方にとって、
このリズムが整うことで、心と体が少しずつほぐれていく感覚が得られることもあります。
私の家は東向きのマンションですが、夜の外廊下の照明がまぶしく、
遮光カーテンを閉めたまま眠るのが習慣に。
朝日が差し込んでいても気づかないまま、無理に目覚ましで起きる日々でした。
そんなときに出会ったのが、自動でカーテンを開けてくれる装置です。
朝が苦手で「カーテンを開けるのすら面倒…」という方にこそ、
この“仕組みに任せる”選択は、とてもやさしい工夫になると感じています。
リズム運動は、体を動かすことだけじゃない
セロトニンは、一定のリズムで繰り返す動きによって活性化されます。
歩く・呼吸する・揺れる・噛む——
こうした“やさしい繰り返し”が、脳にとっての心地よい刺激になります。
音楽とつながるラジオ体操
私が日常に取り入れているのが、3分間のラジオ体操。
アレクサに「ラジオ体操かけて」とお願いすると、音楽に合わせて自然に体が動きます。
義務教育のなかで染みついたリズムって、実はすごい力を持っていますよね(笑)
毎日じゃなくてOK。体に“リズム”を思い出させるだけでいいんです。
子どもも大人も「揺れて整う」トランポリンのすすめ
上下にやさしく揺れるトランポリンは、脳幹に心地よい刺激を与えてくれます。
以前は大きなトランポリンを使っていましたが、ケガの経験から片づけたままに……。
最近出会ったのが、インテリアになじむ安全設計のトランポリンでした。
跳ねるより、そっと揺れるだけでも十分。
リビングに置けるサイズ感で、“整う時間”の相棒になっています。
噛むことも、大切なリズム運動
見落とされがちですが、「噛む」こともセロトニン活性に役立つリズム運動です。
特にガムをリズムよく噛むことで、セロトニン神経が刺激され、気分の安定にもつながることが研究で示されています。
でも、意識したいのは“ガムを噛む”ことだけではありません。
HSP気質の方は、緊張や焦りから「食事中もつい早食いになってしまう」傾向があるかもしれません(私自身、そうでした)。
食べながら次の予定を考えたり、心が落ち着かないまま食べ終えてしまったり——
そんなときこそ、「ゆっくり噛む」を意識してみてください。
しっかり噛むことは、
- セロトニン神経へのリズム刺激になる
- 胃腸への負担を減らし、消化もサポートしてくれる
- 心も“いまここ”に戻してくれる
無理なくできる整え方として、毎日の食事の中で“噛む”を味方につけてみるのもおすすめです。
ただし、食いしばりがある方や顎の違和感がある場合は、無理せず自分に合ったやり方で。
呼吸が速いと、疲れは抜けにくい
施術中、ぐっすり眠っているように見える方でも、呼吸がとても速いことがあります。
本来、眠っているときやリラックスしているときには、呼吸はゆっくり深くなっていくはず。
けれど、浅く速い呼吸が続いているということは、
体の内側では“活動している状態”が続いているということです。
呼吸は筋肉を使う運動でもあるので、速いままだと無意識のうちにエネルギーを使い続けてしまい、
深く休めていない=「疲れが抜けない」状態が続いてしまうのです。
では、なぜそんなことが起きるのか?
背景には、慢性的な緊張やストレスの蓄積、そして“休み方を忘れてしまっている状態”があります。
セロトニンの分泌が乱れていたり、自律神経のバランスが崩れていると、
体は本当は休みたいのに、スイッチを切る方法がわからなくなっている——
そんな状態が、呼吸にも現れているのかもしれません。
Apple Watchなどで呼吸数を可視化すると、自覚と改善のきっかけになります。
でも、「呼吸を整えよう」と意識しすぎると、逆に不自然になることもありますよね。
だから私は、こう伝えています:
「呼吸を整えるのではなく、呼吸が整いやすい体にゆるめていきましょう」
リズムとは、安心をくれる「波」
こうした行動を日々に取り入れていくとき、
もうひとつ大切なのが「続けられるかどうか」です。
HSP気質の方は、まじめで完璧を目指すあまり、
「全部やらなきゃ」「毎日続けなきゃ」と頑張りすぎてしまうこともあるかもしれません。
でも、習慣化にはコツがあります。
それは、“脳を少しずつだますこと”。
脳は“自分のもの”なのに、まるで別人格のように変化を嫌います。
だから、うまく付き合って「安心だよ」と少しずつ伝えていくことが、習慣化のコツなんです。
新しいことをいきなりたくさん始めると、
脳は「これはいつもと違う!危険だ!」と判断して、
辞めさせようとする働きが起こります(これが、いわゆる“3日坊主”の正体)。
だからこそ、
- ひとつずつ取り入れる
- できない日があってもOKとする
- まずは“やってみる”を繰り返す
そうやって、「やさしく自分に馴染ませる」ようにしていくと、
自然と“整う習慣”が、あなたの一部になっていきます。
歩く、噛む、揺れる、呼吸する——
決まった動きを、無理なく、繰り返すこと。
それが、セロトニンを育てるやさしい波になります。
「がんばって何かをする」より、
「そっと寄り添ってくれるものに自分をゆだねる」
そんなリズムのある暮らしが、HSPの方にはぴったりかもしれません。
わたしの整える習慣:使ってよかったアイテム紹介
※以下の商品リンクにはアフィリエイトが含まれますが、
私自身が体験して「これはよかった」と感じたものだけをご紹介しています。
▶ 朝日を無理なく取り入れる【自動カーテン】
起きる前にカーテンがゆっくり開き、体内時計をやさしく整えてくれます。
▶ リビングに置ける【インテリアトランポリン】
跳ねるより「揺れる」を重視した設計で、心地よく整う時間に。
どちらも「がんばらずに整う」をサポートしてくれる、おすすめの工夫です。
おわりに
この「HSPとセロトニン」シリーズでは、
繊細な感受性を持つ方が、自分を責めずに整えていけるヒントをお届けしています。
セロトニンを整えることは、特別なことではありません。
朝の光。
3分のラジオ体操。
呼吸に気づく一瞬。
どれも、大きな努力をしなくても始められる。
「あ、気持ちいいかも」
そう思える感覚が、そのまま整う方向へのスイッチになります。
今日も、あなたの中のセロトニンが、そっと育ちますように。
▶ 次回予告:
次回は「HSPとセロトニン⑤(栄養編)」として、セロトニンを整える土台となる“栄養”に注目します。
「どんな生活習慣をしても整わない」——そう感じている方にこそ知ってほしい、
そもそもセロトニンが“つくられるために必要な材料”とは?を丁寧に解説。
食事内容そのものより、「なぜ必要か」に意識を向けるヒントをお届けします。

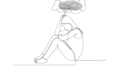

コメント