── 外から見えてきた「やさしさ」という感性
はじめに
最近、SNSや動画の中で、外国人が日本の印象を語る姿をよく見かけます。
「日本人は丁寧」「静かで思いやりがある」「街がきれい」——
そんな声を耳にすると、少し照れくさいような、でも誇らしい気持ちになります。
けれど、ふと思うのです。
この“丁寧さ”や“やさしさ”は、いったいどこから来ているのだろう、と。
【今日の要点】
・日本人の「丁寧さ」や「やさしさ」は“感じ取る力”から生まれている
・この感性は自然とともにあった暮らしの中で育まれてきた
・セロトニンは、この“感じ取る力”を支える心と体のリズムと深く関係している
外国人が驚く「感じ取る文化」
駅で電車を待つ人たちは静かに並び、
お店では「ありがとう」「お待たせしました」が自然に交わされる。
それは、決まりごととして覚えた行動ではなく、
相手の気持ちを“感じ取って”動く日本人の習慣なのだと思います。
外国の方が驚くのも、この「言葉にしないやさしさ」なのかもしれません。
もともと私たちの中にあった“心のリズム”
昔の日本の暮らしは、自然のリズムとともにありました。
朝の光で目覚め、風の匂いで季節を知り、夜には暗闇とともに体を休める。
その中で、私たちは“感じる”ことを通して世界とつながっていたのです。
人もまた、自然の一部。
太陽や風、音、香り——
すべてを“感じ取る力”が、生きるための知恵でもありました。
いつの間にか失われかけた「感じる時間」
けれど現代は、情報も音も光もあふれすぎていて、心が休む間がなくなっています。
便利さと引き換えに、「感じること」より「考えること」を優先するようになりました。
その結果、私たちの中にある“繊細に感じ取る力”が、
うまく働けなくなっているのかもしれません。
繊細さは、弱さではなく“受け取る才能”
たとえば、春の陽ざしの柔らかさにほっとしたり、
人の声のトーンから心の状態を察したり。
そんな瞬間に、「感じ取る力」は静かに動いています。
それは弱さではなく、
人と世界をやさしくつなぐ才能。
この力が十分に働いているとき、
私たちの心は穏やかで、思考も落ち着いていて、
いわゆる「整った状態」に近いのです。
セロトニンと“感じ取る力”の関係
セロトニンは、心と体をつなぐ神経伝達物質。
朝の光を浴びたり、リズムのある運動をしたり、
誰かと穏やかに会話をしたりすると分泌が高まります。
つまり、感じ取る時間を持つこと=セロトニンを育てること。
私たちが昔から自然と行ってきた生活のリズムそのものが、
心の安定を支えていたのです。
いま、改めて思うこと
もしかすると、日本人は昔から、
“感じ取る力”を軸に生きてきた民族なのかもしれません。
それが、現代の私たちが感じる「生きづらさ」や「疲れやすさ」の根っこに、
どこか関係しているようにも思います。
次回は、この“感じ取る力”がどこから生まれたのか——
日本という国の、もう少し深い部分をたどってみましょう。
本記事は、心身のケアやセロトニンに関する一般的な情報提供を目的としています。
診断や治療を意図したものではありません。体調に不安がある場合は、医療機関にご相談ください。
Calm timeでは、日常のセルフケアや心を整える方法をお伝えしています。
🌿 次回はこちら
第2回:感じ取る力はどこから来たのか — 日本人の繊細さのルーツをたどる
(リンク: https://serotonin-bliss.biz/blog/japanese-sensitivity-roots/ )
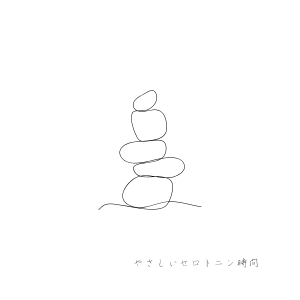
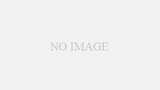
コメント