気づかぬうちに失っていた「余裕」
ヘッドマッサージの学びを通じて、私は初めて「セロトニン」という言葉に触れました。
それは、どこか遠くの知識ではなく、今の私自身にまっすぐ響いてくるものでした。
忙しさと責任感に追われていた日々。
あの頃の私は、常に何かに急かされていて、家族にも、そして自分自身にも、やさしくできていなかった気がします。
思えば、怒りっぽくなったり、必要以上に落ち込んだり、
人の言葉を悪く受け取ってしまったりすることが増えていました。
そのひとつひとつの裏側に、「セロトニン不足」というキーワードがあると知ったとき、
私はようやく、自分の心の状態を客観的に見つめることができたのです。
セロトニンという存在を知って
セロトニンは、脳内で働く神経伝達物質のひとつ。
心の安定やストレスの軽減、さらには眠りの質にも関係していると言われています。
でも、私にとってのセロトニンは、
そういった知識よりも、「ああ、これだったのかもしれない」という直感のようなものでした。
なぜあんなに体が重かったのか。
なぜ朝がつらく、何もかもが負担に感じられたのか。
「理由がある」と思えたことは、
それだけで少し、呼吸がしやすくなるような感覚でした。
施術と、変化のはじまり
ヘッドマッサージには、セロトニンの分泌を促す効果がある。
そう学んでから、私は家での施術を意識的に続けていきました。
最初は、自分のため、というよりも子どもたちのため。
けれど、触れるたびに、自分の心と体にも静かな変化が生まれていったのです。
子どもたちの寝つきが良くなったり、朝の表情が明るくなったり。
「お腹が軽くなった」「頭がスッキリした」と話してくれるたびに、
私の中にも、なにかあたたかな手応えのようなものが広がっていきました。
生活の中でできること
施術だけでなく、日常の中にもセロトニンを増やす工夫があると知り、できることから取り入れていきました。
セロトニンを意識した毎日の工夫
- 朝起きたらカーテンを開けて、光を浴びる
- 朝食をとることを意識する(バナナや乳製品などを取り入れてみる)
- 無理のない範囲で散歩やストレッチを続ける
以前の私は、朝食を抜くことが当たり前のようになっていて、
空腹にならなければ問題ないと思っていた時期もありました。
気づけば、回転ずしが“日常の食事”になっていたことさえあります。
今思えば、栄養の偏りや血糖の不安定さが、
心身の不調につながっていたのではないかと感じています。
また、家族にも同じような兆しがありました。
長女がある日、強い倦怠感とイライラ、発汗などを訴えてきたとき、
看護師としての経験から「低血糖ではないか」と直感しました。
甘いものを摂らせたところ、急速に症状が落ち着いたのです。
後日、病院での検査では異常なしと言われたものの、
これは、検査を受けられる状態=ある程度血糖が安定しているときだったからかもしれません。
実際には、目に見えない「隠れ低血糖」が、生活の中で負担になっていたのではないかと、今では感じています。
また、別の日に、家族の貧血検査の結果として「血糖値が40台」と診断されたこともありました。
医師からすぐに電話がかかってきたほどで、当時は大きな衝撃でした。
空腹でイライラする、お腹が減ると気分が悪くなる――
我が家の出来事として、血糖値の安定が心と体に深く関係しているかもしれないと、改めて感じるきっかけになりました。
そして今では、「食事も心のケアのひとつなんだ」と、自然に思えるようになりました。
食事を整えることの意味
食事を整えるというのは、
「自分を大事にすること」そのものなのだと、今なら思えるのです。
特に、朝食には、セロトニンの材料になる「トリプトファン」という栄養素を含む食べ物(バナナや乳製品、大豆製品など)を意識的に取り入れると、
体と心がゆっくりと目覚めるサポートになるそうです。
知識としては聞いたことがあったけれど、実際に生活を見直してみて、
「ああ、本当に大事なんだ」と、体感できた気がしています。
「触れること」が教えてくれたこと
触れるという行為には、思っていた以上に大きな意味があるのだと、
私は家族への施術を通じて知りました。
温度、リズム、手の重さ、呼吸のタイミング。
それらがそっと整っていくとき、
「今ここにいる」ことを実感できるような気がするのです。
そして、その時間を重ねるごとに、
子どもたちとの会話も、目線も、表情も、少しずつ変わっていきました。
少しの余裕が、家族の空気を変える
私自身も、心が整ってくると、
以前ほど感情に飲み込まれなくなりました。
「なんとかなるかもしれない」
そう思える瞬間が、日々の中に少しずつ増えていったのです。
親の気持ちは、家族全体の空気に影響する。
それを身をもって実感したからこそ、
私はいま「セロトニンの力」に大きな希望を感じています。
そして、誰かのために活かせたら
「こうすればいい」という正解は、きっと人によって違います。
けれど、もしこの経験が、今つらさを感じている誰かの「ヒント」になれるなら。
私は、この手で学んだこと、感じたことを、これからも誰かのために活かしていきたいと思っています。
――次章では、その思いを胸に私が踏み出した「ひとつの決意」について、お話しさせてください。
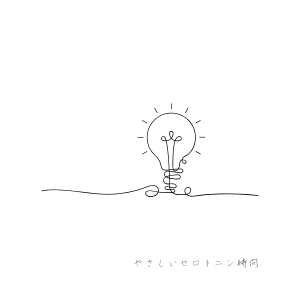


コメント