葛藤を乗り越えた決断
一方で、職場での遅刻や欠勤が増え、
他のスタッフへの負担を考えると、
「このまま仕事を続けていて良いのだろうか」
という悩みが頭を離れませんでした。
家庭と仕事の両立が次第に難しくなり、
子どもたちの体調や生活を考えると、
「家にいるべきではないか」という思いが強くなっていきました。
そんな中、職場から時短勤務の提案を受けました。
「まだ職場に必要とされているんだ」という嬉しさもあり、
これが家族と仕事の両立の第一歩になるのではないかと感じました。
しかし、その話を長女にしたとき、
返ってきた言葉は、私の心に静かに響くものでした。
「その選択は現状と変わらないんじゃない?
今までと違う状況と比べないと……」
起立性調節障害のため、学校に行けない日もあった彼女。
困難を抱えながらも冷静な視点を持っていることに、私は驚きました。
同時に、
- 子どもたちにとって本当に必要な選択とは?
- 家族としてどう向き合うべきなのか?
そんな問いが、私の中で大きくなっていきました。
退職後の新しい生活
仕事を退職し、日々の忙しさから解放された私は、
少しずつ体調が気にならなくなっていくのを感じました。
しばらくは社会での無力感や喪失感に悩みましたが、
それも徐々に薄れていったように思います。
仕事中に頻繁にあった胸の痛みも消え、
頭の中に隙間ができたような感覚がありました。
退職後3か月ほどして、以前から興味のあったヨガを始めることにしました。
一方でPTAの役員を引き受けたことで、
これまでとは違う種類のストレスも経験。
蕁麻疹や声が出なくなる症状が出ましたが、
役割を終えるとともに症状も消えていきました。
子どもたちの体調はなかなか改善せず、
「何か良い方法はないか?」と探し続ける日々が続きました。
「脳疲労」という言葉との出会い
コロナ禍が2年目に差しかかった頃、
「自律神経 改善」と検索したとき、
ヘッドマッサージスクールのサイトに出会いました。
その中で目に留まったのが「脳疲労」という言葉。
臨床で聞いたことのない言葉に、最初は半信半疑でしたが、
「もしかして…」と、徐々に興味が湧いてきました。
スクールを選んだ理由は、
- 施術の根拠が明確であること
- 医学部名誉教授が監修していること
- 海外からも多くの人が学びに来ているという実績があること
「これなら、子どもたちのために役立つかもしれない」
そう思い、私は学び始める決意をしました。
学び始めて感じたこと
最初に驚いたのは、医療従事者が多く通っていたこと。
プロも注目している技術だと実感しました。
講義で学んだ「セロトニンの役割」には、心を揺さぶられるものがありました。
- セロトニンは心の安定やストレス解消に不可欠
- 体のリズムを整える重要な物質
家族の不調の多くが、
セロトニン不足と関係していることに気づき始めたのです。
さらに、施術によってセロトニン分泌が活性化される仕組みを知り、
「これが、私たちに必要なものだ」と確信しました。
家での練習と子どもたちの反応
ヘッドマッサージは、家での練習も大切でした。
最初は「くすぐったい!」「無理!」と笑いながら拒否されることもありましたが、
「少しでも体調がよくなってほしい」という思いで続けました。
練習するうちに私自身も夢中になり、
「もっと上手になりたい」と思えるように。
そんな私を見て、子どもたちが言ってくれた言葉――
「お母さんが楽しそうでうれしい」
その一言は、私の心をそっと救ってくれました。
そして数回目の施術を終えたころ、子どもたちの様子にも少しずつ変化が現れ始めました。
子どもたちの変化:
- 寝つきの悪かった子:自然にスッと眠れるようになり、毎晩「頭のマッサージして」とリクエスト
- 首や肩がこっていた子:マッサージで可動域が広がり、活動量が増加
- 腹痛がちだった子:お腹のマッサージで「お腹が軽くなる」と実感
セロトニンと施術の可能性
セロトニンが心と体に与える影響の大きさを、
施術を通して実感するようになりました。
- 朝の光を浴びる
- リズムのある食事
- 適度な運動
- 家族で笑顔を交わす時間
そんな小さな積み重ねが、
家族の心と体を支えてくれるものなのだと感じます。
「触れることの力」が、子どもたちの心と体を支えている――
その背景には、セロトニンという大切な働きがありました。
👉 次章:【第4章】セロトニンの力――心と体の安定を取り戻す鍵
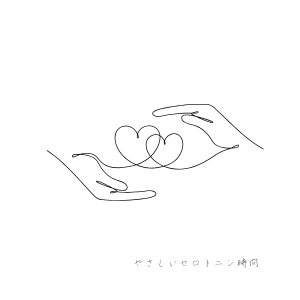
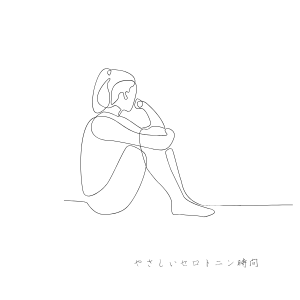
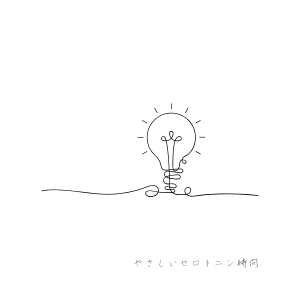
コメント