忙しさの中で、評価を気にしすぎていた私
私の日常は、ただ忙しいだけではありませんでした。
「職場の評価を下げたくない」「周囲の期待に応えなければ」という思いから、
自分でやるべきことをどんどん増やしてしまっていたのです。
さらに、「自分で解決しなければ」という考えが強すぎて、
誰にも頼れず、一人で抱え込むことが当たり前になっていました。
そんな中、ネットに頼って答えを探す日々が続きました。
膨大な情報に振り回され、気づけば心身ともに疲れ果てていました。
これは、2年間どころか、それ以上の長い年月の積み重ねでした。
中学生の子どもに起きた変化
その蓄積がピークに達した頃、子どもたちにも変化が現れ始めました。
中学生の子どもは、
「立ち眩みがする」「ご飯の量が多すぎる」
次第に「眠れない」「朝起きられない」と苦しむように。
最初は「夜更かしのせいでは?」と軽く考えていましたが、
やがてベッドから動けなくなり、学校にも行けなくなってしまいました。
学校を休む日が増え、最終的には笑顔が消えてしまったのです。
疲れ切った表情で、家族との会話も最低限に。
毎朝の欠席連絡と、出口の見えない日々
すぐに終わる電話なのに、かける勇気が必要でした。
出口のないトンネルの中に入り込んだような感覚。
心のどこかで、「もう普通には戻れないのかもしれない」と思い始めていました。
小学生の子どもに現れた不安の兆し
さらに追い打ちをかけるように、
小学生だったもう一人の子どもにも異変が起き始めました。
「お腹が痛い」「気持ち悪い」
不安そうな顔をすることが増えました。
登校前になると「お腹が痛い」と言い、トイレから出られず、
遅刻や欠席を繰り返すように。
最終的には長期にわたり学校に行けなくなりました。
「学校はとにかく疲れる」
「考えすぎて動けなくなる」
といった言葉を頻繁に口にするように。
病院での診断と、見えない不安
病院では「いわゆる敏感さん」と表現されましたが、
具体的な治療法が見つからず、私はますます途方に暮れるばかりでした。
親としての役割と、職場での責任の板挟み
中学生の子どもはベッドで過ごす日が増え、
小学生の子どもは涙を見せる日々。
その一方で、私は職場の管理者という立場にも責任を感じていました。
- 子どもを一人で家に残すことへの心配
- 仕事を休む・遅刻することへの負い目
- 遅れた分の帰宅が遅くなることへの罪悪感
「どちらを優先すればいいのか」――答えが見つかりませんでした。
退職を申し出たこともありましたが、
すぐには辞められない状況や
「社会的な役割がなくなるのが怖い」という思いもあり、
一歩を踏み出せずにいました。
家族を犠牲にしてしまったという気づき
結果的に、私は「他者を優先する」行動を取り続けてしまっていました。
その中で、唯一わがままを言える存在だった家族を犠牲にしていたのです。
中学生の子どもの笑顔が消えた顔を見るたび、
胸が締め付けられるような思いになりました。
小学生の子どもが「お腹が痛い」と訴えるたび、
「自分がもっと強ければ」と責めるばかりでした。
私が本当に守るべきだったのは、
目の前にいる子どもたちの「心」だったのに――。
そんな後悔が、私の中に深く残っています。
自律神経の乱れによる症状と対処法
今振り返れば、子どもたちの症状の多くは、
自律神経の乱れによるものでした。
そして後から気づいたことですが、
それらは「セロトニン」と深く関係していたのかもしれません。
中学生の子どもの症状:
- 立ち眩み
- 疲労感
- 朝起きられない
- 眠れない
医師からのアドバイス:
- 水分・塩分をしっかり摂る(血圧を上げる)
- 決まった時間に起きて朝日を浴びる
- 軽い運動を取り入れる(リズムのある動作)
小学生の子どもの症状:
- 腹痛
- 不安感
- 過敏性の増加
- 過緊張
- 疲労感
対応として勧められたこと:
- 腸内環境を整える食事(乳製品やバナナなど)
- 安心できるリズムある生活
- 過敏さへの配慮と声かけ
しかし、当時の私はそれを実行する気力すら湧きませんでした。
心身ともに限界だったのです。
調べすぎて、さらに迷う
いつもの私なら、病名や治療法を徹底的に調べて、
最善の方法を探そうとするはずでした。
けれど、このときの私は違っていました。
情報をひたすら集めてはいたものの、
そのどれを信じていいのか分からず、ただ不安が膨らむばかり。
- 小さなことが負担になる
- 情報を調べるほどに不安が膨らむ
- 優先順位がわからなくなる
- 疲れていても休めない
→ そして、ますます悪循環へ…
家庭も職場も、どちらも守れない現実。
振り返ると、疲れ切った状態では効率的な判断や行動ができず、
むしろ自分自身が問題を複雑にしてしまっていたことに気づきました。
子どもたちの変化と、行動への転換点
――そんな日々の中で、子どもたちの体調や表情に変化が現れ始めたことで、
私の意識は一気に「自分」から「子どもたち」へと向かっていったのです。
何か行動を起こさなければ。
そう思いながらも、具体的な一歩が見えず、私はただ立ち尽くしていました。
そんな中、「自律神経」「ストレス」「疲れやすさ」などの言葉を検索するうちに、
後に大きな転機となるある“考え方”や“方法”に、私は出会っていくことになります。
👉 次章:【第3章】心と体を整える――ヘッドマッサージとの出会い
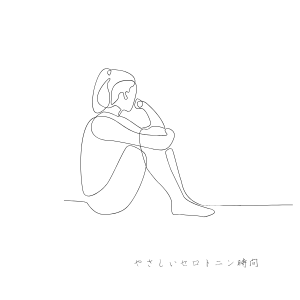


コメント